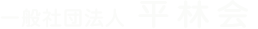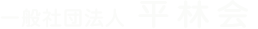近畿中国森林管理局の1階「森林のギャラリー」に3月6日~27日まで「国産材と早生樹材の活用」をテーマに日本木材加工技術協会関西支部早生植林研究会がポスター展示を行った。会期中、ギャラリーに展示された「センダン」の輪切りが来場者の目を惹いていた。
「センダン」は日本各地に自生する広葉樹で中之島や住吉公園等の街路樹に多用されている。ところが広葉樹の宿命、通直の木が少なく商材としては不向きだった。同研究会(京都大学村田功二教授やユニウッドコーポの横尾國治氏らが中心)は熊本県が開発した「芽欠き」手法で通直な材の生産が可能だと知り、平林会の賛同得て、平成26年(2014)4月、熊本県から運ばれた「センダ」ンの苗木10本(最終的には20本)の植樹が「平林ウッディーク」内で行なわれた。輸入比率の高い広葉樹(それも早生樹)を自前で育てようという計画は林野庁にも認められ林業白書にも記載された。
4月13日開幕の万博では近畿各府県産材を活用する提案が認められ、各府県は地元産材の丸太を使った半割のベンチを作り提供することになった。そこで大阪府木連は「センダン」に着目、平林会の協力を得て「平林ウッディパーク」に育つ10年生の「センダン」の中から一番成長の良い1本を伐採、万博用に提供した。
【写真】の通り、100年生の「ヒノキ」と10年生の「センダン」の差は歴然としている。あれから10年、「センダン」は各方面で注目を浴び植樹が進められているという。